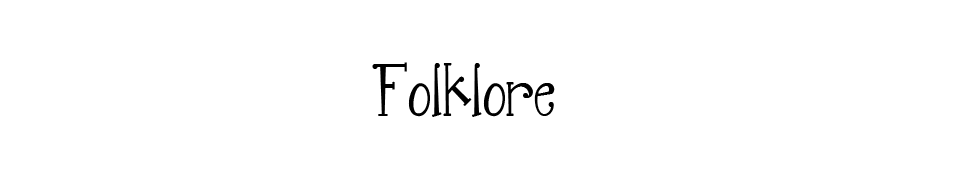フォルクローレ
英語のfolklore(民俗学・民間伝承などの意)をそのままスペイン風に読んだ言葉だが、今日では特に民俗音楽、あるいはそれにもとづいて作られた民衆音楽をさしてこう呼ぶことが多い。
さらに日本では、習慣により中南米のアンデス地帯および南方の諸国(ペルー・ボリビア・エクアドル・チリ・アルゼンチン・パラグアイ・ウルグアイ)の民俗音楽をさして、普通こう呼んでいる。
実際にはメキシコ・キューバ・ブラジルその他の国ぐにでも自国の民族音楽田園風な伝統音楽をさしてフォルクローレという言葉を使っているのではあるがこの理由は、日本で初めて知られたフォルクローレがユパンキ・ファルーなどのアルゼンチン田園音楽であり、つぎにペルーのコンドルは飛んでいくがヒットしてアンデス系の音楽がある程度盛んに紹介されたせいであろう。

アルゼンチンのブエノス・アイレス周辺およびウルグアイには、ガウチ(牧童)たちによってはぐくまれた、おおむね歌とギターによる抒情的な歌、軽快な舞曲が伝わっている。
代表的な曲種にミロンガ・シフラ・エスティーロ・ガト・マランボなどがある。
チリおよび西アルゼンチンの一部にはやはりギターを主体のしたフォルクローレがあるが、趣は微妙に異なる。活発な舞曲クエカ、抒情的な歌のトナーダに代表される。
パラグアイは歌、ギターとともにアルパが盛んで、ポルカ・ガローパ・グアラニアなどが軽妙に、また甘美に演奏される。
アルゼンチン北東部は、隣接するパラグアイとよく似た音楽をもちながら主になる楽器はアコーディオンとギター。主要な形式はチャマメである。
ボリビア、ペルー、アルゼンチン西北部、チリ北部などアンデス地帯はインディオ音楽の伝統がひときわ強く生きており、リズム楽器の種類も多い。
ケーナ、サンポーニャ、チャランゴ、ボンボほか の楽器によって広く普及するウァイノ、歌曲ヤラビほか たくさんの形式が演奏されている。
踊りの音楽より歌として発達したペルー首都のバルス(ワルツ)も独特だ。
エクアドルには、ペルー、ボリビアと一味違った哀調豊かな一群のフォルクローレがある。
フォルクローレで使われる民族楽器
フォルクローレで良く使われる代表的な楽器をご紹介します。
ケーナ(quena)
 南米アンデス高原地帯で用いられる尺八タイプの縦笛。竹のように堅い蘆を用い長さ40cm弱、吹口にU字形の切込みをもち音孔は表側に6ヶ、裏側に1ヶあり、下端は開いている。
南米アンデス高原地帯で用いられる尺八タイプの縦笛。竹のように堅い蘆を用い長さ40cm弱、吹口にU字形の切込みをもち音孔は表側に6ヶ、裏側に1ヶあり、下端は開いている。
ペルー・ボリビア・アルゼンチン北部などの音楽に使用され、日本でも1970年代に普及し、ギターなどを組み合わせてアンデス風の音楽を演奏するアマチュアグループが各地に生まれている。この楽器の起源はインカ文明以前にさかのぼると推定される。![]()
サンポーニャ(zampona)
 ペルー、ボリビアなどアンデス地帯で用いられるインディオ系の楽器。
ペルー、ボリビアなどアンデス地帯で用いられるインディオ系の楽器。
ヨシなどの管を長さの順に並べて結わえつけ、音階を吹けるようにした。パンの笛の仲間で、大小さまざまな種類がある。
アイマラ語でシーク、ケチュア語でアンタラと呼ぶこともある。
歴史の古いもので考古学出土品にも多くみられる。![]()
チャランゴ(charango)
 南米の民俗楽器、アンデスの山岳地帯(ボリビア・ペルー・アルゼンチン北部など)で用いられる小型ギターで、起源は17世紀ごろスペインから移入されたギターの一型にある。
南米の民俗楽器、アンデスの山岳地帯(ボリビア・ペルー・アルゼンチン北部など)で用いられる小型ギターで、起源は17世紀ごろスペインから移入されたギターの一型にある。
通常5組の複弦を張り、一般のギターより高い音が出る。胴体は木製のこともあるが、小動物アルマジロの硬い甲羅をそのまま楽器の胴体として用いたものが多く、このことが外見上の最も顕著な特色となっている。
ただし表面板はつねに薄い木材で作られる。主として5音音階(ドレミソラの音階)にもとづくアンデス地方の民俗音楽を演奏し、和音をかき鳴らして歌や踊りの伴奏をする。音色の可憐さと相まって独特な情緒をもつ楽器である。
なお1970年代に至りペルー、ボリビアに動物愛護の見地からアルマジロ捕獲禁止令が出されたため、現在は木製の胴体が主流となる。![]()
ギター(guitarra)
 イベリア半島で最も好まれた楽器ギターは、中南米にも16~17世紀から普及し各地に定着してそれぞれ固有の音楽を奏でるようになった。初期に行われた複弦ギターの伝統は今日も各地に残っており、ブラジルのビオラ、キューバのトレス、コロンビアのティプレなどにその顕著な例を見ることができる。一般的なスパニッシュ・ギターも広く盛んに用いられている。
イベリア半島で最も好まれた楽器ギターは、中南米にも16~17世紀から普及し各地に定着してそれぞれ固有の音楽を奏でるようになった。初期に行われた複弦ギターの伝統は今日も各地に残っており、ブラジルのビオラ、キューバのトレス、コロンビアのティプレなどにその顕著な例を見ることができる。一般的なスパニッシュ・ギターも広く盛んに用いられている。![]()
チャフチャス(chaqcha)
 チャフチャスはアンデス地方のパーカッション(リズム楽器)で宗教儀式や祭りで太鼓と一緒によく使われる。チャフチャスは羊・豚・山羊・ラマ・アルパカなどの蹄や木の実を細長い布に糸でくくりつけ作られる。手に持ったり、足首につけてリズムを刻む。チャフまたはチャフチャスと呼ばれている。
チャフチャスはアンデス地方のパーカッション(リズム楽器)で宗教儀式や祭りで太鼓と一緒によく使われる。チャフチャスは羊・豚・山羊・ラマ・アルパカなどの蹄や木の実を細長い布に糸でくくりつけ作られる。手に持ったり、足首につけてリズムを刻む。チャフまたはチャフチャスと呼ばれている。![]()
ボンボ(bombo)
 ボンボはスペインの軍隊太鼓が原型とされる大太鼓アルゼンチンの平原地帯のフォルクローレで使われていたものがボリビアなどアンデス地方の音楽にも使われるようになった。毛が生えたままの動物の生皮を張っていることが最大の特徴である。皮は牛・山羊・リャマなどのものが使われる。胴体はアルゼンチンの木をくりぬいたしっかりした作りに比べ、ボリビアのそれはベニヤ板を丸めて釘で止めただけの簡便な作りのものが多い。(写真はワンカラと呼ばれる大太鼓)
ボンボはスペインの軍隊太鼓が原型とされる大太鼓アルゼンチンの平原地帯のフォルクローレで使われていたものがボリビアなどアンデス地方の音楽にも使われるようになった。毛が生えたままの動物の生皮を張っていることが最大の特徴である。皮は牛・山羊・リャマなどのものが使われる。胴体はアルゼンチンの木をくりぬいたしっかりした作りに比べ、ボリビアのそれはベニヤ板を丸めて釘で止めただけの簡便な作りのものが多い。(写真はワンカラと呼ばれる大太鼓)
ラテンアメリカ音楽
ラテン・アメリカ音楽は日本では、俗にラテン音楽、中南米音楽ともいう。
アメリカ大陸にスペイン、ポルトガル、フランスなどのヨーロッパ人が入り込み
さらに彼らが奴隷として使役するためにアフリカ人を連れて来て、原住民(インデイオ)の音楽、ヨーロッパ音楽、アフリカ音楽の3者がさまざまに衝突し、ラテン・アメリカ音楽と総称される数多くの音楽型式を作り上げてきた。そしてこれは、メスティソ系とムラート系の二つのグループに大別することができる。
メスティソ系のラテン音楽とは、原住民の音楽とヨーロッパの音楽との衝突と融合で生じたもので、国別では、メキシコ、ペルー、ボリビア、チリ、アルゼンチン、パラグアイなどの音楽がこれに属する。コロンビア、ベネズエラ、ブラジルにはメスティソ系とムラート系が共に共存し、キューバ、ドミニカ、プエル・トリコなどカリブ海地域は、ムラート系が主体であるがメスティソ系も存在する。メキシコ、アルゼンチンなどのメスティソ音楽はややヨーロッパの要素が強く、ギターが楽器の中心となり、民俗舞踊と結びついた6/8拍子のリズムをもつものが多い。メキシコのソン、アルゼンチンのサンバなどがその例である。
それに比べて、ペルー、ボリビアなどアンデス高原地域には原住民の伝統が残存しケーナと呼ばれる笛などスペイン侵入以前のなごりをとどめる楽器がいまだに使われたり、ときにケチュア語、アイマラ語など原住民の言語で歌われたりする例もすくなくない。
こうしたメスティソ系の音楽に対し、ムラート系のラテン音楽は、ヨーロッパの音楽とアフリカの音楽との衝突もしくは融合によって形成された。キューバのソン、ブラジルのサンバなどがその例で、カリブ海の島々およびパナマ、コロンビア、ベネズエラ、ブラジルの海岸部に分布し、ペルーやエクアドルの一部にもみられる。ヨーロッパから伝えられたギターも盛んに用いられるが、アフリカ人の伝統である打楽器(太鼓、がらがら、鉦などの類)がビートのかなめとなり、2/4拍子のリズムのものが多い。ムラート系の音楽も踊りと
結びついている例がほとんどだが、一般にメスティソ系の民俗舞踊が一定のフォーメーションをもち、音楽もそれに合わせて展開するのに対し、ムラート系のそれは踊り方が自由で即興的なため、音楽も即興の余地を残した2小節、4小節の単純なパターンの反復という形をとることがきわめて多い、この反復パターンの一つに「コール・アンド・レスポンスcall-and-response pattern 」というのがある。これは独奏(もしくは独唱)者の自由な即興にゆだねられた2小節と、合奏(もしくは合唱)による一定の形をもつ2小節とが、交互に現れての反復である。ワーク・ソングの交互唱に源をもつように思われるこのパターンが、ムラート系の音楽の重要な特徴となっている。
このように、メキシコ、キューバからアルゼンチン、チリまで非常に広範な地域に及ぶラテン・アメリカ音楽も原住民の残存する地域と、原住民が滅ぼされた後にアフリカ人が導入された地域(カリブ海諸島と大西洋沿岸部)とに、おおまかに分けてとらえることができ、距離的には遠く離れているにもかかわらず、メキシコとアルゼンチンが類似点の多い音楽をもち、キューバとブラジルが類似点の多い音楽をもつ。もちろん子細にみていくならば、ラテン・アメリカ各国の音楽はきわめて千差万別で、さらにそれぞれの国の音楽も多種多様である。また、複雑な歴史的展開と地域的な広がりからすれば、この多様さは当然のことであって、むしろそれにもかかわらず、この大陸全体の音楽に多くの共通性が存在するのを見落としてはならない。大陸全体に共通するものを要約して言うならば、大衆的なダンス・リズムの生命力ということになろう。その生命力は、何よりもラテン・アメリカ音楽の雑種性からきていると考えられる。
メスティソ系にしろムラート系にしろ、雑種文化という点は同じである。まったく別のところから出てきた文化と文化とがぶつかりあった結果として生まれた雑種文化は、根強い生命力と、また同時に強靭な大衆性を備えている。雑種文化は大衆の底辺に根づいてこそ育ちえた文化だからであって、ラテン・アメリカには独自のエリート文化(例えばヨーロッパにおけるクラシック音楽のような)は存在しない。その大衆性と雑種文化なるがゆえの国際性をもって、ラテン・アメリカ音楽は早くからヨーロッパやアジアにも浸透し、アフリカ音楽にさえ影響を及ぼしてきた。そして、アングロ・アメリカ(北アメリカ)のムラート音楽ともいうべきジャズやロックとともに、今日の世界のポピュラー音楽の主流を占めるに至っている。
インディオの音楽
ヨーロッパ音楽、アフリカ音楽がアメリカ大陸に到来する前の固有の音楽はインディオの音楽の中にその姿が求められる。インディオの音楽文化は部族によって特色や発展度が異なり一概には言えない。生活と密着した形で伝承されてきたものが多く、たとえば宗教、労働、舞踊などに結びついている。一般的に言ってメロディーは単純だが、表情には欠けていない。とくにアンデス地帯では半音なしのペンタトニックによる旋律が多く「東洋的」に感じられる情緒をかもし出す。楽器の点では本来弦楽器をまったく、あるいはほとんど持たなかったことが特色である。インディオ古来の楽器と言えるのは、管楽器(笛、ラッパ、オカリーナの類)か打楽器(太鼓、がらがらの類)で、それらの中にはたて笛のケーナ、パンの笛のサンポーニャ、あるいはマラカスのように、こんにち世界中に知られたものもある。